京進保育グループでは、プログラミング教育についての学びを深め より良いカリキュラムをご提供できるよう、社員一丸となって研鑽に励んでいます。
そのひとつとして、今回は日本マイクロソフト株式会社様のご協力で実現した講義の様子をレポートします。
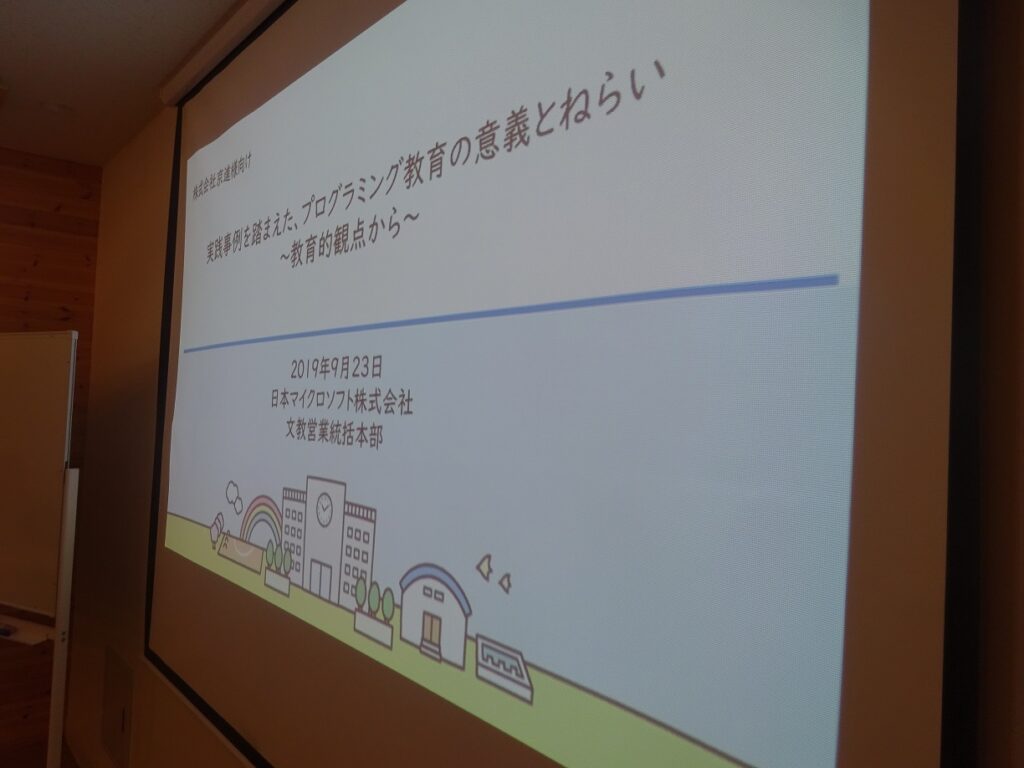
講義をしていただいたのは、日本マイクロソフト株式会社 パブリックセクター事業本部 文教営業統括本部
の猪原氏とマイクロソフト認定教育イノベーターで明治大学サービス創新研究所のタツナミ氏。
この日は、保育グループの現場管理者を対象にご講義いただきました。


猪原氏からは「プログラミングとは / プログラミング教育のねらい」を中心にお話いただきました。
そもそも「プログラミング」とは何でしょうか 🙄
「プログラミング」と「コーディング」は似た意味として使われがちですが、「コーディング」とはプログラム言語で記述すること。
それに対して、「プログラミング」とは単にコードを書く(コーディング)だけでなく、「“何を創造するか”“どう苦難を乗り越えるか”といったものづくり全体のこと。より広いプロセス全体」を指します。
AIやRPA(ロボットによる業務プロセスの自動化)が台頭するこれからの社会で、人間の仕事は「自ら考え、自ら創り出すもの」に変わっていきます。
だからこそ、「問題解決型思考」である「プログラミング的思考」がこれからを生きる子どもたちにとって重要になっていくことをご教授いただきました。

小学校へのプログラミング教育導入に携わられているご経験の中で感じられることとして、『プログラミング教育は専門的で難しいものと受け止められがちだが、決してそうではない。なぜなら、プログラミング教育で重要なことは、先生が教え込むことではなく、子ども同士で取り組み、解決するために、先生が手を差し伸べることであるから。そういった意味では、先生はプロの専門家である必要はない』というご指摘もありました。
私たちも幼児向けにプログラミング教育を導入するにあたり、「教え込むのではなく、『子ども自身の自ら考え、解決し、創り出すちから』が存分に引き出されるよう手を差し伸べること」、このことを主軸に置いてカリキュラムを構築していきます。

タツナミ氏からは、プログラミング教育の実践ご経験や海外でのプログラミング教育の現状を交えて、プログラミング教育に必要な観点をお話いただきました。
✤プログラミング教育は、必ずしも「プログラマーになりましょう」というためだけにあるものではない。
✤プログラミングは生活の中でも役立つものであり、家庭でも、仕事でも、人間がいかに効率的に生きるか、に資するもの。
✤「効率性」という、リアルの世界ではなかなか瞬時には体験しずらいものを、プログラミングを通して体験できる。
✤体験できるから、子どもたちは興味や好奇心をもって学びに向かえる。それがプログラミングの醍醐味。
世の中には、子ども向けのプログラミング教材として利用可能なものがたくさん提供されていますが、タツナミ氏曰く、『ただ与えるだけではゲームや遊びで終わってしまう。学びに向かうよう、大人がうまく導くことが大切』とのこと。
京進保育グループのプログラミング教育では思考力を育み、学びへの気づきを持たせられるよう「設定した課題に取り組む時間」と「子どもたちが自由に創造性を発揮する時間」をバランスよく配置していきます。
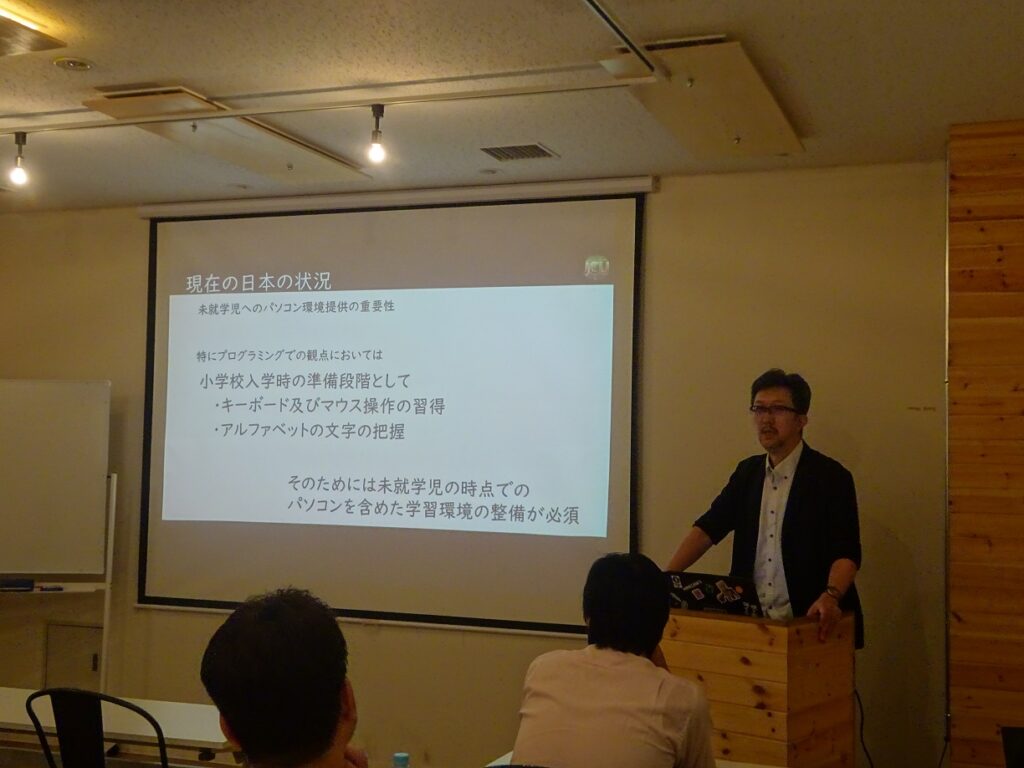
大変印象的だったのは、2020年度から小学校での必修化が予定されていますが、それ以降、国内でもプログラミング教育のレベルは徐々に上がっていくはずだ、というご指摘。
小学校入学準備段階で習得しておくべきプログラミングのレベルも3年後、5年後を踏まえて、今から考えておく必要がある、世界を見渡せば日本人はもっと危機感を持たなくてはいけない、とのご指摘に、改めて身の引き締まる思いでした。
小学校以降、本格的なプログラミングに取り組む際は、やはりキーボードやマウス操作が必要になってきます。そのためには、幼少期からアルファベット文字の把握ができていることも有意義になってくるとのことでした。

京進保育グループでは日々のイングリッシュタイムで、子どもたちの英語への関心を高めるとともに、英語を話す素地作りにも力をいれています。
こういった面でも、京進保育グループの「イングリッシュタイム」や「知育タイム」と、新しく導入される「プログラミング教育」が有機的に一体となって、子どもたちの成長に寄与していくのではないかと改めて感じました。
参加した現場の責任者からは「より学びを深められた」との声もたくさんきかれました。
これからの京進保育グループにも、ぜひご期待ください!